『木挽町のあだ討ち』やりました、直木賞! ― 2023年07月19日
7月2日の投稿で、ご紹介した本が、直木賞を受賞しました!
『木挽町のあだ討ち』。著者は、永井 紗耶子さん。
おめでとうございます!!
この小説は受賞できるかも……とひそかに期待していました。
そして、私の二つ目の目標、
〈直木賞を受賞する前にその作品を読了する〉
というのも、ついに達成しました。ダブルでうれしいです。
ますますおススメしたい本になりました。


おススメの本『木挽町のあだ討ち』 ― 2023年07月02日
先ほどまで、大河ドラマ「どうする家康」を涙ながらに見ていました。
「鎌倉殿ロスだから、家康は見たくない」という友人もいます。マツジュンがタイプでないという友人もいます。……といった感じで、私の周りでは、ちょっとばかり視聴率が低そうです。
私はといえば、いつものように、日曜午後8時は大型テレビにかぶりついて見ております。
現代劇みたいでチャンバラシーンも少なく、重厚感もなく、従来の大河ドラマがお好きな方にはつまらないもしれません。風変りすぎて。
現代人が描く〈戦国時代劇〉だと思えば、それなりにおもしろいですよ。
なんといっても、私にはこれを見る理由があるのです。
月に一度、浜松のカルチャースクールで、「初めてのエッセイ」の講師を務めています。浜松愛にあふれた生徒の皆さんの影響で、私もすっかり浜松びいきになりました。
そして、ちょうど一年前の今ごろ、浜松城を訪ねました。興味も倍増するというものです。
前置きが長くなりました。
そうそう、大河ドラマの今回は、家康の妻と息子の信康が謀反の罪で、自害するシーン。今生の別れが描かれました。
それを見ながら、思い出していたのは、昨晩読み終えた本のことでした。
それが、『木挽町のあだ討ち』。著者は、永井
紗耶子さん。
じつは、今月発表になる直木賞の候補5作の中のひとつで、唯一の女性作家です。
私はいつも女性を応援したい。男女格差が先進国の中でもほぼ最下位の日本、女性に頑張ってほしいのです。というわけで、読み始めたのでした。
初めて読む作家ですが、同じ大学の文学部卒という経歴に親近感がわきます。
これまでの著書には時代小説が多いようですが、流れるような読みやすい文章、武士道についても、市井の人々の生き方なども、肩肘張らない深い洞察が感じられます。
そして、なんとも胸のすくあだ討ちでありました。
ところで、6月2日の記事に、「直木賞を読む」というエッセイを載せています。
現在も直木賞作品を読破するという目標は続いていますが、〈直木賞を受賞する前にその作品を読了する〉という二つ目の目標も持っています。
いまだ達成できたことがないのですが、この本はいけるかもしれない、とひそかに期待しています。
今年上半期第169回直木賞の発表は、7月19日です。
さて、ドラマの自害シーンと、小説の中のあだ討ちシーン。同じか否か。
ぜひ、皆さんも、だまされたと思って、この本を手に取って確かめてください。

ほぼ2000字のエッセイ:直木賞を読む ― 2023年06月02日
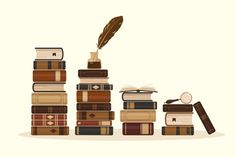
油絵を習っているという友人に聞いた話だ。彼女の絵の先生は、
「本物を見なさい。展覧会に行ったら一等賞の絵だけ見ればよい」と言うのだそうだ。
絵に限らず、文章も同じではないか。一等賞の文章を読もう、できればおもしろいものを、といつも思っていた。ある時、はたとひらめいた。そうだ、直木賞受賞作がいい。大衆文学の一等賞だ。エッセイの上達のためにも、ちょうどいいのではないか。
そこで私は、柄にもなく目標を打ち立てた。10年ほど前のことだ。
《西暦2000年から現在までの直木賞受賞作を読破する》
昭和10年に文藝春秋社が始めたこの賞は、著名な作家陣10名ほどが選考にあたり、毎年7月と1月、その半年間に発表された小説の中から選ばれる。受賞作2作品のこともあるし、該当なしのこともある。
ところで、私の目標はなぜ2000年からなのかというと、それには理由がある。1999年上半期の受賞作に、かつて読み始めたのだがどうしても読み進むことができずに投げ出した作品があったのだ。佐藤賢一著『王妃の離婚』。3分の1まで頑張ってみたけれど、何がおもしろいのがわからないままギブアップしてしまった。これを課題図書としないための年代設定だった。
それから3年ほどで目標は達成できた。それ以後も継続中で、新しい受賞作を欠かさず読んでいる。この1月に発表された2作を読み終えて、合計58冊、すべて読破し続けている。
それにしても『王妃の離婚』は、なぜそれほど相性が悪かったのだろう。謎を解くためにも、再挑戦してみようかと思うこともある。
私のもくろみどおり、読破した一等賞の作品はどれも本当にすばらしい。おもしろい。裏切られることはない。
なんといっても、読書の幅が広がった。自分で思うに、私は何事にもあまり好奇心旺盛ではない。この目標がなかったら、自分から手を伸ばすのはたいてい、お手軽な恋愛小説とか、のめり込んでしまうような推理小説とか、できれば舞台は現代で、リアリティがあって共感しやすいもの……といったところだった。知らないジャンルは避けてきた。
そんな私が、戦国時代だろうと明治時代だろうと、異国の物語だろうと未知なる生業の物語だろうと、機械的にページを繰っては文字列を追い続ける。そのうちに、しっかりと小説の中に埋没して、胸躍らせながら楽しんでいる自分がいるのだ。みずから定めた目標は、期待以上に効果があった、と自画自賛している。
ところが、である。2年前の受賞作『テスカトリポカ』佐藤究著。これにはまいった。初めて選考委員を恨んだ。なぜこれが受賞作なのかと。
おどろおどろしい古代遺跡の一部のような表紙も、一度では覚えられないタイトルも、古代アステカ文明の神様らしい。舞台は1990年代のメキシコから始まり、日本、ジャカルタにも及んでいる。麻薬密売組織の抗争。謎の密売人、闇の医師、プロの殺し屋たちの暗躍。古代文明の残虐ないけにえの儀式。巨額の資金が動く臓器売買という闇のプロジェクト……。最初から殺戮シーンが冷酷に克明に描かれ、物語が展開するにつれて、それらは狂気を増してエスカレートしていくのだ。
ちょうどその頃、朝日新聞デジタル版に、選考委員を退任した北方謙三氏のインタビュー記事が載った。彼は私の目標と同じ2000年以来の就任だったというから、選考の様子や印象的な作品など、話の内容がすべて理解できておもしろかった。
『テスカトリポカ』に関しては、選考委員の中でも意見が分かれたという。残忍な描写はともかくとして、子どもを犯罪に巻き込む場面を表現する必然性があるのかと、北方氏が選考会で疑問を呈したところ、「男って弱いのね。私は平気よ」と言われたそうだ。ちなみに、現在の選考委員は男性3名、女性6名という比率。残酷シーンにも冷静でいられる女性が増えたということか。しかも、彼女たちはそれをも含めたこの作品の文章力の高さ、小説としての優れた部分をきちんと見極めていたのだ。
この記事を読んで、目からうろこだった。私が負の感情ばかりにとらわれて、小説としてのおもしろさに思いが至らなかっただけだ。古代のいけにえの儀式を現代の犯罪によみがえらせるという奇抜な構想は、かなりの書物を読み、各地に足を運び、綿密な情報を集めたことだろう。佐藤究はすごい作家なのだ。気がつくと、結末を知りたくて、残酷シーンにおののきながらも、昼も夜も読み続けた。
これほどエネルギーを消費した読書はなかった。読んでよかったとはいまだに言えないけれど、とりあえず読了してノルマ達成できたことに安どする。
当初の目的「エッセイの上達のため」は二のつぎ、三のつぎだ。
さてさて次回の受賞作は、いかに。


伊吹有喜著『彼方の友へ』を読んで ― 2021年04月16日

「面白いから読んでみて!」と友人が貸してくれたのがこの本。実業之日本社文庫の分厚い一冊です。
小説は、平成29年下半期の直木賞候補にもなっています。
時は昭和12年。佐倉ハツという16歳の少女が、憧れの少女雑誌『乙女の友』の編集に関わるようになるところから物語は始まります。最初は雑用係として、やがて編集部のれっきとした一員になり、さらには小説も執筆するようになっていく。
しかし、少女の成長していく様をつづっただけの物語ではありません。昭和12年から昭和20年といえば、日本が戦争に向かって走っていき、やがて敗戦を迎えるという時代背景がある。この時期の小説がそこから逃れることはできません。
前半は、雑誌の販売が軌道に乗っていた頃の話が展開します。出版社の社長や編集長、主筆と呼ばれるイケメン風の男性、ハーフのような美形の画家、気の強そうな女性執筆者たち……。こと細かく描かれたたくさんの人物に囲まれ、少し気の弱そうな主人公ハッちゃんが、右往左往しながらも彼らに支えられて頑張る毎日がつづられます。
ところが、半分を過ぎた辺りから、がぜん事態は深刻になっていくのです。
世の中に戦争の影が暗く落ちてくる。日本国民一丸となって戦争に勝利するための行動をとらなくてはならない。紙の無駄遣いのような少女雑誌はけしからん。華美な装飾はけしからん。敵性語はけしからん……。
雑誌はどんどんと追い詰められ、男たちは戦争に駆り出されていきます。
そして、空襲が東京を覆いつくす日々。ハツたちの体験した空爆の様子に、ただただ息をのむばかりでした。
若い頃の物語に、時々さしはさまれるのが、現代の介護施設に暮らすハツ。車いすで、うとうとしては、遠い日々の夢を見たりしています。
ある時、そこへ若い訪問者が現れて面会します。ハツが90歳を過ぎた今、最後の最後に、彼の言葉によって物語の全景が見えてくる。昭和の昔に埋もれてしまったような謎のかずかずが明らかになるのです。
前半の詳しい情報は、すべて伏線だったということに気づかされます。戦争がもたらした悲劇。それを乗り越えて進もうとする人々の熱い思い。そして、恋……。謎のまま残された部分さえも、いとおしく思えてきます。
前半を読んでいた時、いまいち入り込めないなどとちょっとでも思ってしまった自分に恥じ入りながら、後半は涙が止まりませんでした。
そして、巻末の解説によると、この小説はあくまでもフィクションだけれど、実在する『少女の友』という雑誌がモデルになっているのだそうです。1908年に実業之日本社から創刊され、1955年まで続き、当時の少女たちを夢中にさせたとか。執筆者には、川端康成、吉屋信子、堀口大學などなど、一流の作家たちが名を連ね、イラストは中原淳一が人気を博していたといいます。
残念ながらこの雑誌は、私の少女時代にはすでにこの世にありませんでしたが、2009年に、『少女の友』100周年記念号というものが発行されたとのこと。さっそく調べて図書館に予約を入れたところです。
私より、少し先を行くお姉さま方なら、きっと覚えておいでではないでしょうか。そんな皆さまにおススメしたい一冊です。

おススメの本、遠田潤子著『アンチェルの蝶』 ― 2020年09月05日
前回のおススメ本に続き、今回はこの本をおススメします。
ところで、『ザリガニの鳴くところ』の少女の母親が、なぜ子どもを置き去りにして家を出たのか。それは夫の暴力でした。子どもたちも父親に愛想をつかして出て行ってしまうのです。
この小説もまた、その部分が偶然にも同じでした。
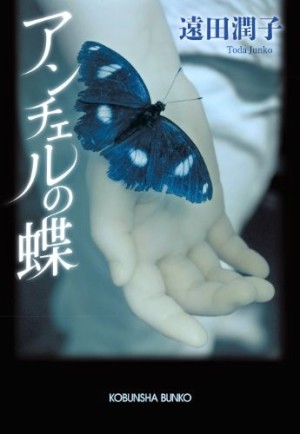
物語は、主人公・藤太が大人になっている現在から始まります。痛む膝を引きずるようにして、ひとりで飲み屋をやっている。荒んだ雰囲気で、ときに強い酒をあおって酔いつぶれる。そんな藤太が、突然小学生の女の子を預かる羽目になる……。謎めいたストーリーを予感させます。
そして物語は過去へ。
藤太の父親も、酒に酔っては暴力をふるうどうしようもない男でした。母親が去り、父親と二人で暮らしながら、高校にも行かせてもらえない。飲んだくれの父親に代わって、小さな飲み屋を手伝わざるをえない。それでも父親は息子を殴る。どん底の暮らしでした。
中学生の藤太には、二人の親友がいました。同じクラスの優等生男子と、バレリーナを夢見る少女と。三人は固い友情で結ばれ、互いに信じあい、支えあいながら、中学校生活を続けるのです。
三人の共通点といえば、父親がひどすぎること。ろくに仕事もせず、賭け麻雀をしては、酒に酔い、とんでもない悪事に手を染めている……。
三人の絆の意味が少しずつ解明され、秘密めいた話の真実が明かされていきます。
それでも、暗く重い話の先に、藤太の明るい希望が見え隠れするのですが……
そこから先は、ご自身で読んでみてください。
三人の仲間も、藤太の店の常連たちも、暗い過去を抱え、世の中に背を向けているようでも、どこか正直にまっとうに生きたいと思っている。どん底から這い上がろうとしては、希望と絶望とに翻弄される。読み手は、そんな姿から目が離せない。もっともっと先を読みたくなるのです。
ちなみに、遠田潤子氏は、私が今一番注目している作家です。
今年上半期の直木賞でも『銀花の蔵』が候補になりました。いずれ受賞するのでは、と熱い期待を寄せています。
