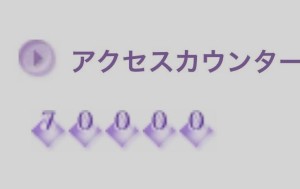現状のご報告 ― 2023年12月06日

前回の記事を載せてから、あっというまにひと月がたちました。
脳卒中で倒れてリハビリ病院に入院中の77歳の義姉と、今まで義姉と二人暮らしをしていたのに突然独りになった102歳の義母。2人の心配を抱えていることは、これまでにも書いてきました。
そのさなか、2ヵ月ほど前になりますが、今度は長男が、よりによって自分の誕生日に、バスの中でパニックを起こして乗客に迷惑をかけてしまったのです。
翌日から、住んでいるグループホームから職場への通勤に、付き添うことになりました。夫はバスと電車に同乗、私は車で送迎。福祉サービスの支援は受けられず、実費を支払ってヘルパーさんにお願いする日もありますが、なんとか欠勤をしないで続けています。
ところが、今度は義母が、体調を崩して一人暮らしができなくなり、わが家に移ってきました。
万事休すとはこのことです。長男の送迎のこともあり、予定していた旅行もすべてキャンセル、趣味のあれこれも休会、今月はエッセイ教室の仕事もお休みにさせてもらいました。
夫と2人で「3人分の介護」をしながらも、義母と半身まひの義姉がこれまでどおり一緒に暮らせる介護付き老人ホームを探して奔走しました。ようやく、実家の近くに良いところが見つかり、義母が体験入居をしたうえで、「ここにする」と言ってくれたのです。やれやれ!
今は契約に向け、あちこち駆け回ってもろもろの手続きを進めているところです。
1月半ばには、義姉も退院して、ホームに入居することになります。
それが落ち着けば、ひとまず肩の荷が下りることでしょう。
長男のトラブルについては、今はまだあまり詳しくは書けませんが、3ヵ月ほど通勤に付き添って、来年からはまた単独で行動させるつもりです。
しかし、「今回の一件は障害者の人権にかかわる社会的な問題でもあるのだから」と、主治医の先生から言われました。近いうちに先生から紹介していただいた弁護士に相談することになりそうです。
そのことについても、いずれご報告できればと思います。

数字のメモリー ― 2023年10月21日
「シャラリーン!」
10月6日、見事な秋晴れのドライブ日和。1年ぶりに一時帰国をした娘を乗せて、湘南の海を目指していました。運転中に、ナビがなんとも軽やかでハッピーな音を発したのです。
初めて聞いた助手席の娘が、「なにこれ!?」とびっくり。
最近の車は安全のためにやたらと音を発しては警告してくれるのですが、これは警告ではなく、お知らせ音。
数キロ走ると、ふたたびシャラリーン!
今度はさすがに、娘が素早くナビ画面を読みました。
「もうすぐ記念距離メモリーです」
……と書いてあるかどうか、じつは私もさだかではない。1秒ほどしかそのお知らせが出ないので、読み終えないうちに消えてしまうのですね。
またもシャラリーン!
車の走行距離には、7777㎞という数字が出ていました。
その後は、お知らせ音は鳴らなくなりました。
3年前、初めてこの音を聞いたときは、私もびっくりしたものです。
なになに?? 画面に何か文字が……、と思っているうちに消えてしまう。これでは、思わずブレーキを踏みたくなって、事故を起こしかねないのでは、と心配になりました。
助手席の夫が「設定で鳴らないようにできるはずだよ」と言ったのでしたが、ちょっと考えてそのままにしました。こういう遊びごころ、嫌いではない。
それから10日ほどたって、またしてもシャラリーン!
今度は、後ろの席で、長男が「な、なんだ?」とびっくり。
この日は8000㎞の記念距離達成でした。
ところで、このブログのアクセス数も、今月1日に80,000回を記録しました。残念ながら、ジャストの写真を撮りそこないましたが、皆さまが覗いてくださるおかげです。
いつも、ご覧いただき、どうもありがとうございます♡

ちなみに、前回の記念メモリーは、2021年7月6日の70,000回でした。