2000字エッセイ:「娘が巣立つとき」 ― 2015年08月02日
娘が巣立つとき
社会人4年目になる娘が、職場に近いマンションを借りて独り暮らしを始める、と言いだした。
メガバンクの総合職として就職した娘は、とにかくハードな勤務を続けている。早朝、ご飯も食べずに出かけ、夜遅く帰宅する。テレビを見ながら一人で夕食をすませると、そのままリビングのソファで爆睡。朝5時に携帯電話のアラームが鳴り響き、あわててシャワーを浴びて出勤する。
とくに最初の2年間は、都内でも1、2を争う超多忙な支店勤務によく耐えた。現在は、大手町の本部に移り、乗り換えなしの片道50分の通勤だが、それでもハードな生活であることに変わりはない。
ところが、さぞ疲れているだろうと思いきや、休日はほとんど家にいない。旅行に登山、競馬にゴルフ、そして飲み会……。娘なりのストレス発散なのだろう。たまに在宅のときは、夕方まで寝ていて、家事手伝いはおろか、自分の部屋さえ散らかったままだ。
「とてもとてもこのままでは、独り暮らしは無理ね。まして、二人暮らしをや……」
私は冗談半分でため息をついたものだ。いくらタフな娘とはいえ、体を壊しはしないかと、はらはらするばかりだった。
1時間でも睡眠時間を増やしたいという彼女の理由に、異を唱える気持ちはない。地方に転勤の可能性も十分にあったので、いずれは、と心づもりもしていた。
しかも、娘は高校生のうちから、マンションの4軒隣に住む母のところで寝泊りをしてきた。お風呂は母のところで入り、食事はわが家で食べていたが、最近では朝食も夕食も外ですませるから、週に1、2度しか顔を合わせないこともある。片足は家を出ているような感じだったのである。
次の週末に、「清澄白河のマンション、仮押さえしたから」と娘が言ってからは速かった。いい物件はすぐに押さえて契約も早くしないと、ほかにも希望者が何人も待っているらしい。それも不動産業者の手なのかもしれない。父親はのんきに母親に一任のかまえだ。とにかく、娘と一緒に出かけていった。
「清澄白河」と聞いても、以前、田園都市線の終点だったから知っているだけで、降りたのは初めて。大手町からは3つ目の駅だ。歩いてみると、街のあちこちで巨大なスカイツリーが顔をのぞかせる。清澄庭園に近く、東京現代美術館の最寄り駅でもある。すし屋、和菓子屋、豆腐屋などが並ぶ商店街があり、お寺の屋根もあちこちに見え、いかにも下町らしい風情が漂うなかに、新しい感覚のショップが入り混じって、魅力的な街に変貌しつつあるようだ。
めざすマンションは、駅から住宅街を歩いて5分ほど。築2年で、新しい設備が整い、快適に住めそうだ。買い物に不便はないし、治安もいいという。私はGOサインを出した。私まで、新しく別荘ができるような浮き立つ気分になっていた。
そして、7月の3連休、猛暑のなか、引っ越しを敢行した。初日は自宅から小さな荷物を送りだし、翌日向こうで受け取る。それまでに買っておいた電化製品や家具なども、3日間のうちに配送される予定だ。街を歩き回って買い物をしたり、収納を手伝ったり、私は娘とともに肉体労働に明け暮れた。娘も、自宅に戻ってきて後片付けやごみ処理など、夜中までがんばっていた。
一人でやらせておこうかとも思ったが、あえて私は口を出し、手を出した。娘はこれからもなにかと母親の世話になる必要が出てくるだろう。そんなときには遠慮せず頼ってほしい。だからこそ、まだまだいける、と印象付けておきたかったのである。
最終日には、自宅で最後の荷物を車に積み込み、首都高を飛ばした。そして、日が暮れかかる頃には、娘と手を振って別れた。
「ありがとうございました」
「気をつけるのよ」
行きは助手席に娘がいた。帰りは一人だ。渋谷辺りで渋滞する。右側には真っ赤な夕日がまぶしい。やがて、ピンク色の夕焼け空がひろがっていく。正面にはシルエットの富士山が見える。BGMは、娘の好きな嵐の、それも別れの歌が……。
不覚にも涙があふれて、視界がぼやけた。
後日談がある。母から聞いた話だ。
「あの子、前の晩にお風呂をピッカピカに磨いていったのよ。今までお風呂掃除なんてしたこともなかったのに。まさしく、立つ鳥跡を濁さず、だったわ」

ダイアリーエッセイ:黒い蝶が舞う朝 ― 2015年08月03日
朝、リビングのカーテンを開けると、黒い蝶がベランダにいた。
アゲハチョウの一種だろうけれど、ほとんど模様もなく真っ黒だ。
ひらひらというより、ゆらゆらという感じの弱々しさで、ガラス戸の向こうを着かず離れず飛んでいる。まるで、部屋の中に入れて、と訴えているかのように見える。
……誰かの化身だったりして。
起きたばかりのぼうっとした頭で、ふと思った。
死んだ人が蝶になって帰ってくる、という話をどこかで読んだような気がする。
それを信じるような趣味は持ち合わせないが、貴婦人が葬儀に身につけるドレスをまとったようで、その力ない飛翔も、不吉な想像をかき立てるに十分ではあった。
このところ、毎晩寝る前に、先日直木賞を受賞した東山彰良著『流』を読んでいる。幽霊と昆虫が出てくるくだりがあるのだ。しかも、かなりショッキングだった。
私の思考回路がその影響を受けてしまっているのかもしれない。
蝶は、鮮やかなマリーゴールドやサフィニアにも、美味しそうな香りのゴーヤの花にも近寄ろうとはせず、ただふわふわと、庭の上を漂うように舞っていた。15分もいただろうか。やがて、姿は見えなくなった。
それにしても、黒い蝶の出現はなぜ……?
「虫が知らせる」という言い方も、古くからあるではないか。
……やっぱり、何かの〈知らせ〉だったりして。
そうだ、ブログに書いておこう。みんなに喋ってしまおう。
黒い妄想が、ただの杞憂に終わるように。

朝日新聞「継ぐ記憶 私たちに戦争を教えてください」 ― 2015年08月06日
今年から選挙権も手にした息子たちの世代に、今こそ自分たち自身のこととして、戦争と平和についてもっともっと考えてほしい。これから先もずっと、戦争をしない平和な日本に生き続けることができるよう、歴史の教科書の中のことではなく、自分たち自身の現実問題としてとらえてほしい。
そう思ったからです。
おそらく記事の趣旨も、若い世代に読んでもらう狙いがあったのではないでしょうか。

それは、毎年のことながら、夏休みをのほほんと過ごしているわが家の大学生に、母親からのささやかな宿題です。
これを読んで、何を感じたか、自分の言葉で話してみて。
さて、回答はいかに……?
シリーズ4回目では、福士蒼太さんが初めて原爆ドームを訪れます。
そして、当時、出征してしまった男性社員に代わって路面電車の運転をしていた女性二人から話を聞きました。
継ぐ記憶 私たちに戦争を教えてください:4
福士蒼汰さんは見つめる
被爆した広島の街で 助け合う少女の強さ
(クリックすると、朝日新聞デジタルにリンクします)
今日は、広島に原爆が投下されてから70年目の「原爆の日」。

ダイアリーエッセイ:「水をしっかり飲む」 ― 2015年08月08日
今日は、横浜市磯子区民センターで開催の〈磯の綴り会〉というエッセイ教室の日です。
いつものように、車で出かけました。
首都高を降りて、赤信号で停車。すると、あらら、私の前で信号待ちをしていた軽トラックが、赤信号はそのままなのに、するすると走って行ってしまいました。青になったのは歩行者信号だけですよー!
しばらく行くと、また前の乗用車が、信号無視で行ってしまった……。
2回も立て続けに信号無視を目の当たりにするなんて、変な日です。
みんな暑さで頭がぼーっとしているのかな。気をつけてくださいよ。
さて、今月のエッセイのテーマは「水」。なくてはならない水だからでしょうか、どのエッセイも、テーマをぴたりと水に合わせて、ぶれない作品に仕上がっています。
その中のKさんの作品のタイトルが、「水をしっかり飲む」。
あるドキュメンタリー番組の紹介から始まります。イギリス人の探検家が、さまざまな自然環境の中で、体ひとつで生き抜くための方法を教えてくれるのだそうです。暑さ寒さをしのぎ、天敵から身を守り、食べ物をどうやって確保するか……。
サバイバルのなかでも重要なのは、飲み水です。食べなくても3週間は生きられるけれど、水無しでは3日が限度だとか。脱水症状が進むと、思考能力が鈍り、パニックに陥って生存率がぐっと下がるといいます。
絶対に飲んではいけないのは、海水。意外にも、山に積もった雪や川の水もNG。バクテリアに汚染されている可能性があるそうで……。
彼のエッセイは、まさに立て板に水のごとく、よどみなくすらすらと読める文章で、数々のサバイバル術をフムフムと興味深く読ませてもらいました。
近年の日本の猛暑は、熱中症で亡くなる人もいるほど。大自然に放り出されなくても、私たちはコンクリートジャングルでサバイバルを余儀なくされているのかもしれませんね。
帰り道、気がつくと、赤信号を突っ切っているではありませんか。おっと、危ない、危ない……。
そして、いつもの首都高の入り口も、なぜか通り過ぎてしまいました。暑さでボーっとしているのは、私も同じかも?!
ぐるりと回って同じ高速入り口に戻ってくる間に、片手でごそごそとバッグを探り、水筒のお水をしっかり飲みました。
皆さんも、くれぐれもご用心。まずは、お水をしっかり飲みましょう!

Windows10アップグレードのてんまつ ― 2015年08月14日
Windows10に無償アップグレードをお考えの方、少しでも迷っているのでしたら、おやめになったほうがよさそうです。
私は、先週、インストールしました。
いつもなら、新しいものにはすぐ飛びつかない私なのに、しかも、ITはまったくの素人なのに、何を血迷ったか、魔がさしたか、脳みそが熱中症になりかかっていたのか、自分でもわかりません。無謀なことをしたものだ、と後からいたく後悔しました。
テレビを見るアプリは、最初から使えなくなることが分かったのに、なぜその時点でやめようと思わなかったのかも不思議です。アップグレードに伴ってアンインストールしてしまいました。夜な夜な、部屋でこっそりお気に入り番組を見る楽しみが消えました。
アップグレード後は、とにかく状態が不安定で、エラー&再起動の繰り返し。しかも、スタート画面が開かず、ブラウザのMicrosoft Edgeも、アプリストアも開きません。ほかにも不具合がありそうです。
アナログ的に言えば、既存の組織に新しいものがのさばって入ってきたので、拒絶反応が出ている、摩擦が起きている、というところでしょう。
ネット検索してみると、私一人ではなく、同じ症状で苦しんでいるユーザーがたくさんいるようでした。
MS社としては、そのあたりの情報が欲しかった。それゆえの無償アップグレードだったのでは……? 〈無償〉は結局高くつく、ということです。
解決策を見出すべく、毎日ネット検索してはIT専門家のお知恵を拝借し、あれやこれや試みましたが、しょせん素人、何の効果もなし……。
改善策を講じた修正パッチができるまで、じっと待つしかないのでしょうか。やれやれ……
***************************
と、昨日はここまで書きました。
しかし、その後もどうしてもイライラが募り、耐え切れず、以前のバージョン、Windows7に戻すことを決断。うまく戻せなくなる例もあるそうなので、躊躇しましたが、ひとまず成功です。テレビ視聴のアプリも、晴れて再インストールできました。
無償アップグレードは、何が起きても解決できる自信のあるユーザーのためのサービスですね。私がモルモットになるにはひ弱すぎた。いい勉強になったと思うことにします。
いずれ、今のパソコンを買い替える日も来るでしょう。そのときこそ、安心してWindows10搭載の新機種を買いたい。ちらりと味わった新機能も、悪くはありませんでしたから。
私の個人的な体験が、皆さんのうちのどなたかを救うことになればと思い、ご紹介しておきます。

『わたしの戦後70年』発行 ― 2015年08月15日
今年4月29日に、「あなたにとっての〈戦後70年〉を教えてください」
と題して、記事を書きました。
戦後70年にあたる今年、『わたしの戦後70年』という合同作品集を刊行するプロジェクトに関わっている、という内容です。
その本が、ようやく完成の運びとなりました。
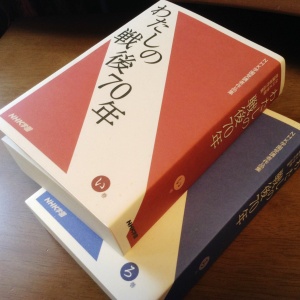
この本の筆者136名の方がたは、私が専任講師を務める通信講座の受講者の皆さんです。その関係で、文章関連の講師7名で、寄稿作品に対するアドバイスや原稿の校正を手がけてきました。
70代、80代が中心ですが、中には90代の方がたもいます。ほとんどが手書きの原稿には、戦争で亡くなった肉親への思い、大陸から引き揚げてきた体験談などがつづられています。
あるいはまた、戦後の復興を支えた企業戦士の苦労話もありました。ご自分で道を切り開き、成功を手にした方が、晩年になった今、満ちたりた思いで自分の歴史を書き残す。それはそれで素晴らしいことです。
どんな作品も、最後は「戦争は二度としてはならない」「平和であり続けるように」という切実な願いとともに結ばれています。
ちなみに、作品集の巻頭言は、ジャーナリストの池上彰さんが「さまざまな人生が立ち上る」と題して執筆しました。
……これを戦後80年、90年と続け、ずっと「戦後」であってほしい。これは私の願いですが、この本にまとめられた人たちの願いでもあるはずです。
と結んでいます。
ところで私は、あとがきの中で、次のようにつづりました。
……8月15日の玉音放送については、多くの作品で語られています。その日から、食糧難や社会の混乱など、新たな闘いが始まったはずです。とはいえ、戦後の復興に向けて立ち上がっていく日本人のたくましさには、圧倒されるばかりです。……
その日本人のたくましさはどこからきているのだろう……と、疑問を抱いていたのです。
先日ある番組を見て、答えを見つけました。
NHK BSプレミアム「玉音放送を作った男たち」がそれです。
当時の情報局総裁下村宏氏は、昭和天皇自らの肉声で国民に呼びかけることこそが、敗戦後の日本を立ち直らせる大きな力になる、と信じて尽力したのです。クーデターが起き、身の危険にさらされながらも、玉音放送は予定どおりに8月15日正午、ラジオから流れ、国民一人ひとりの心に届いたのでした。
また、昨日、映画『日本のいちばん長い日』を観てきました。
この映画では、本木雅弘さんが演じる昭和天皇が、国民を想う慈愛に満ちた姿で描かれています。
「国民は苦しんでいる。私の名によって始められた戦争を、私の心からの言葉で収拾できるのなら、ありがたく思う」
こうして、ご聖断がくだされ、玉音放送が実現しました。
「堪え難きを堪え、忍び難きを忍び、以て万世に太平を開かんと欲す……」
それまでは「現人神」だった天皇陛下が「国民の象徴」となり、戦後の国民の心を支えてきた。そのスタートとなったのが、玉音放送だったのではないでしょうか。
この映画によって、改めて腑に落ちた気がします。
今日は、70年目の終戦の日です。

映画『この国の空』を観る ― 2015年08月18日

新井晴彦監督の映画『この国の空』を観てきました。
戦闘シーンのない戦争映画。銃後の人々を静かに描いた作品です。
隣の席のオジサンは、退屈したのか寝息を立てて眠っていました。
エンドロールのときに、ヒロインの里子が茨木のり子さんの詩を読みます。
わたしが一番きれいだったとき
まわりの人達が沢山死んだ
工場で 海で 名もない島で
わたしはおしゃれのきっかけを落としてしまった
わたしが一番きれいだったとき
誰もやさしい贈り物を捧げてはくれなかった
男たちは挙手の礼しか知らなくて
きれいな眼差だけを残し皆発っていった
わたしが一番きれいだったとき わたしの国は戦争で負けた……
里子の周りから、子どもやお年寄りはみな疎開していき、若い男性は赤紙が来て戦争に行ってしまう。19歳の里子は、38歳の妻子ある男性に、青春の血を燃やすしかなかった。
ふと、私の母も彼女と同じ年頃だったことに気がつきました。母も22歳で終戦を迎えています。
もう、モンペじゃなくてスカートをはいていいんだ、ということがうれしかった。でも、はこうにもスカートは一着もない。オシャレをしたくても、何もなかった、と言います。
私は、きらびやかな物であふれかえっている都会の街を歩く気にもなれず、重い気持ちで帰宅しました。

おススメの本、東山彰良著『流』 ― 2015年08月20日
ご存じ、今年上半期の直木賞受賞作品で、つまり最新の受賞作である。
【西暦2000年以降の直木賞受賞作を読破する】という目標を打ち立ててから、何年たっただろうか。いつもぐずぐずしていると、あっという間に半年ごとの選考時期が来て、新しく受賞作が増えていく。
現在は全部で41作品。増えたばかりの1編を読んでみることにした。
この作品は、目標達成のためでなかったら、食わず嫌いの私が自分から手に取ることはなかったろう。台湾を舞台にした青春ミステリー。中国人の祖父の物語……。とくに私の興味を引く内容でもないし、日常との接点も見当たらない。ノルマという縛りだけで機械的に電子本を購入し、iPad-miniに流し込んで読み始めた。
のっけから、排せつ物の話……。冗談じゃないなわぁ。
途中からは、ゴキブリの大群が出現。それだけで音を立てて本を閉じたくなる。それでも、大群はゴキブリホイホイを船のように移動させる――ホイホイの窓からも黒いギザギザの肢が何本も突き出され、まるでケンブリッジ大学のボート部のようにホイホイを漕ぎ進んだ(原文)――というシーンには、真夜中の読書の最中に声を立てて笑ってしまう。
主人公は、喧嘩ばかりする。暴力シーンがたびたび繰り返されるのも閉口した。しかも、コミック雑誌の劇画が目に浮かぶような文章だ。どうして男の人っていうのは、こういうやくざ映画みたいなのが好きなんだろうか。
これが、文才?
……などなどと、ケチばかりつけながら読み進んでいた。「おススメ本にはなりえない」と思っていた。60パーセントを読むまでは。
ところが、半分を超えると、だいぶ印象が変わってきた。主人公の骨太な人格と繊細なハートの熱さがじわじわと私を魅了し始める。家族への情の深さ、悪友への思いやり、そして、恋。
気がつけば、海を越えた壮大なミステリーのとりことなり、文字どおり、物語の奔流に押し流されていた。
いやはや、すごい小説だった。臭くて、乱暴で、熱くて、まじめで、いとしくて、せつなくて……。
面白かった。
おススメです!

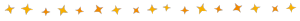
母に代わって戦争体験記を〈前編〉 ― 2015年08月31日
11年前のこと。娘が中学3年のとき、「家族の戦争体験を書く」という宿題が出ました。
私も娘とともに、当時81歳だった母の話を聞きました。母は娘にもよくわかるように、やさしく解説しながら、話してくれました。
それまでも、私は何度となく母から戦争の話を聞いてきましたが、ちょうどいい機会なので、母の代わりに書き残してみようと思い立ちました。
それがこのエッセイです。「私」というのは母自身のことです。
原稿用紙10枚という長編ですので、2回に分けてお届けします。
*****************************

(母が16歳のときの写真です)
昭和12年、日本が中国と戦争を始めた頃、私は女学校の生徒でした。今で言えば高校生です。東京の世田谷に、両親と兄、姉、弟とともに暮らしていました。
戦争が始まってもしばらくは、今までどおりに通学し、勉強していましたが、そのうちに昼休みや放課後を利用して、慰問袋を作るようになりました。戦地に出征した兵隊さんに贈るのです。まず、手ぬぐいを半分に折って両端を縫い、その中に食べ物や手紙を入れて封を閉じます。缶入りのドロップなどを入れたように思います。作文の苦手な私は、兵隊さんへの手紙に何て書いていいのか分からなくて困ったものでした。
戦地から負傷して帰って来た兵隊さんも目につくようになりました。負傷兵はみな白い着物を着ていたから、目立ったのかもしれません。
女学校には、ときどき負傷兵の方が講演に来ました。中国の地図を広げては、日本がいかに攻撃して勝利を上げたかを話してくれます。今でも覚えているのは、とても話し上手で面白かった海軍の将校さんと、もう一人、対照的に話のつまらない陸軍の将校さん……。じつはこの人こそ将来の舅になる人だとは、神のみぞ知る、だったのです。その女学校に娘さんが二人通っていた関係で講演に来た、ということは後からわかったことでした。
女学校卒業後は、家政専門学校に入学。家庭科の教師になるための学校です。派手な着物に袴をはいて、しゃなりしゃなりと通学します。雨の日には、駅から学校まで華やかな色の傘の列が続いたものでした。
けれども、日本は太平洋戦争へと突入し、どんどん戦争の色に染まっていくのです。女学生といえども派手ではいけないといわれて、入学した年の夏休みには、制服を作らされました。上着とスカートの、地味な紺色のスーツでした。
また、学校の校庭で軍事訓練をするようになります。すぐ近くの市ヶ谷に近衛師団があったので、そこから若い将校が教官としてやって来て、私たちは鉄砲を担いで行進の練習をしたりしました。
このころ、日本人の男性は全員、二十歳になると兵隊検査を受け、赤紙と呼ばれる召集令状が来たら、軍隊に入らなければなりませんでした。
赤紙が来ると、周囲の女性が「千人針」を作り始めます。それは、手ぬぐいのようなさらしの布に、千人分の女性の縫い玉を集めたもので、出征兵士は敵の弾除けとしてお腹に巻いていくのです。まず、筆の柄のおしりに赤い墨をつけては布に判を押し、千個の印をつける。その輪の中に、赤い糸で一人一針縫っては玉を作ってもらいます。女性たちは、兵士が無事に帰って来られるようにと、祈りを込めて縫いました。なかなか千人分も集めるのは大変なので、一人が年齢の数だけ玉を作ることにしたり、寅年生まれの人にはその倍縫ってもらったりしました。
私の長兄は、当時発電所に勤務しており、台湾に住んでいたので、現地で召集されました。衛生兵として陸軍病院で働いたそうです。
次兄は中国へ送られました。おもにトラックの運転手として物資の輸送にあたったそうです。二人とも激戦地に駆り出されることもなく、終戦後、無事に復員してきました。
しかし、長姉の夫は、二度目の招集で南方へ行かされることになります。東京港から出発の前日、主計中尉だった彼は、人目をしのぶようにして私の家に訪ねてくることができました。そのとき、母だけが在宅していました。
「おかあさん、あとの家族のことをよろしく頼みます」
彼はその場で遺書をしたため、急いで帰っていきました。母一人、涙ながらに見送ったのでした。
結局、彼の乗った船は南方へ向かう途中で撃沈されたそうです。姉のもとに届いた骨壷には、わずかな遺髪だけが入っていたといいます。
*****************************
〈後編に続く〉
